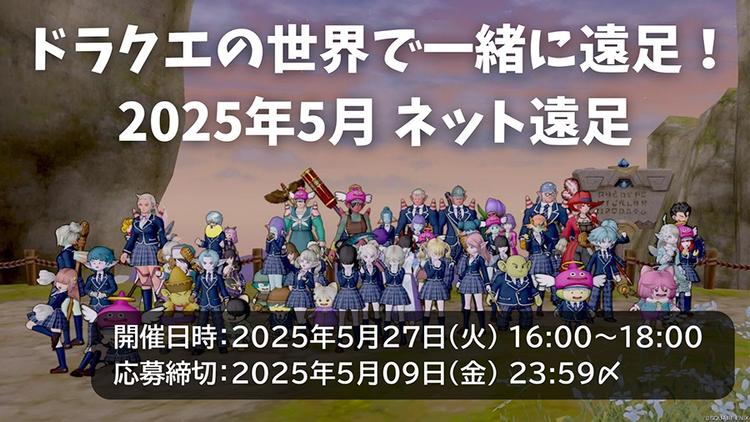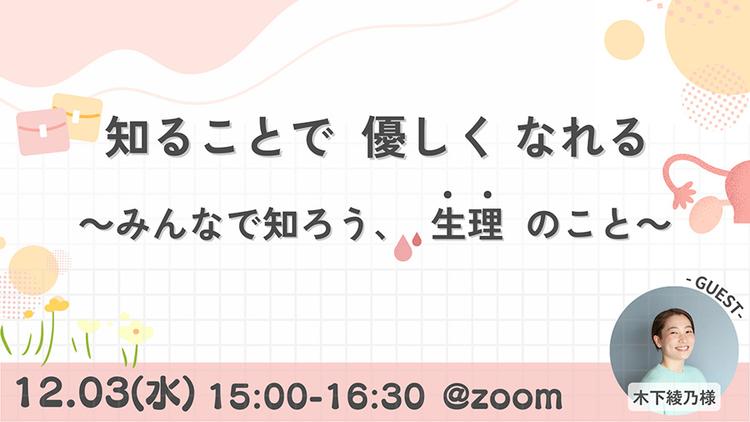※このブログは、仙台キャンパスの3年生、ひなさん、そらさん、さわさん、ゆうとさんに協力してもらいました。(学年は2021年3月時点)
昨年度の受験が終わった時期、とある日の放課後、仙台キャンパスで頑張ってきた3年生たちの有志に、N高生活を振り返るオンラインインタビューをしてみました。その風景をのぞいてみましょう……。
今日はいろいろお話を聞かせてもらいます。よろしくお願いします。まずは簡単にみなさんの進路を教えてください。
ひな:管理栄養士養成課程のある四年制大学に進みます。
そら:文化社会学部心理·社会学科です。
さわ:デザイン系にしました。
ゆうと:国際系の大学です。
多様な進路ですね!いつ頃、どのような理由で進路を決めましたか?
ひな:進学する大学の教授の研究に興味を持ったことをきっかけに、3年生に進級したばかりの4月に決めました。
そら:3年生になってから、少しでも呼吸のしやすい生き方をしたいという思いがきっかけで、社会問題やそれに関わる人の心理に関心を持ちました。心理学と社会学を両方学べる学科を探し、受験に臨みました。
さわ:高校2年生の秋頃です。家から通える距離で、デザインの分野の中でも、イラストや工芸、グラフィックなど幅広く学べる大学だったため、楽しそうだと感じました。
ゆうと:高校1年生の頃から興味を持っていました。英語に加え、各国の文化も深く学べるということで志望しました。日本が抱えている待機児童や児童虐待などの児童福祉問題に対し、既存の仕組みに加えて、東アジア諸国が持つさまざまなシステムや文化背景からアプローチしたいです。

コロナ禍ということもあ相って、大変なこともあったと思います。受験勉強で苦労したことにはどんなことがありましたか?
ひな:AO入試対策の時間がどのくらい必要か不透明だったことが大きかったです。一般受験とは内容が違いすぎるので、受験対策のバランスを取るのも難しかったです。共倒れの恐怖が常にありました。
そら:AO入試の二次試験の録画面接が辛かったです。編集することができないので、上手くできなかった場合、最初から最後までもう一度、撮り直さなくてはならず、本番を何度も繰り返しているようで体力をかなり消耗しました。正直、二度とやりたくないです(苦笑)
さわ:AO入試のプレゼン面接の対策です。あがり症で、練習段階ですでにド緊張していました。本番で頭が真っ白にならないように、話したい内容を頭に叩き込みました。
ゆうと:進学予定の大学から合格をいただける前に、2つの大学に落ちていたので、モチベーションを保てない時期があり、辛かったです。担任の先生との面接練習やティーチング・アシスタント(以下、TA)の方に悩みを話すことで不安を解消しました。

それぞれに苦難を乗り越えたうえで掴み取った進路ですね、本当におめでとうございます!N高生活の学びはどんなところに役立ちましたか?
ひな:まず印象的だったのは「Nゼミ(※1)」です。答えのない問題を多角的な視点で捉え、エビデンスを元に議論することが習慣づいたのは大きかったです。データ収集力や柔軟性が身につきました。議論を交わすなかで、自分が人生で大切にしたいもののブレない軸が見えてきました。
次に、私が提案して仙台キャンパスの定番となった「朝プレ」です。朝礼後にみんなに5分間のプレゼンをするこの習慣から、伝えたい内容を簡潔にまとめる力がつきました。伝えたいことがちゃんと伝わっているかが不安で、何回も言い換えて同じことを言う癖があったため、回りくどくて何が言いたいのかわからないと指摘されて悩んでいましたが、改善されていきました。
※1 「Nゼミ」とは、毎週放課後に少人数でグループディスカッションをおこなう会のことです。
そら:一番役立っているのはスケジュール管理です。普段の生活や課題解決型学習(PBL)「プロジェクトN」など、期限や目標を意識してスケジュールを組み、実行することが多かったため、自分で予定を管理して反省する習慣ができました。
さわ:プレゼンをする機会がたくさんあったことで、人前で話すことの苦手意識が薄れました。どういう言い方や順番で話せばより伝わるかということを、考えながら話せるようになったのがとても大きな収穫です。
ゆうと:N高生活で小論文と英語に重点を置いて勉強したことが実りにつながりました。小論文では、繰り返し添削指導を受け、コンテストで受賞することができました。英語では、基礎学習を積みつつ、どこにいても勉強できるというN高の特色を活かし、カナダへの短期留学も経験しました。これらの学びは、受験や社会問題への興味などにもつながりました。
いろいろなことを学び、吸収し、活かせていますね!N高生活で最も好きだったことは何でしょうか?
ひな:AL(※2)面談です。TAの方々からの的確な助言が心に響きました。自分の思っていることや将来について整理することもできました。
※2 AL制度(アクティブラーナー制度)とは…N高では、アクティブラーニング(能動的学習)を取り入れています。積極的に学ぶ意欲のある生徒がさまざまなことに挑戦し、教養、思考力、実践力を主体的に高めることをサポートするためにできた制度。ALに認定された生徒は自身の目標達成のために時間割の一部を担任の先生と相談してカスタマイズすることができます。
そら:先生やTAの先生とのおしゃべりの時間です。私自身が話好きであることに加え、放課後や面談のときなど話せる機会が多く、考え方や経験など聞いていて学びになりました。
さわ:一番は「Adobe(※3)」が使えたことです。他の学校にいたら触れる機会がなかったと思います。自分の得意なことを見つけられて、選択肢が広がり将来デザイン系の職業に就きたいと思うきっかけになりました。
※3 角川ドワンゴ学園の生徒は「Adobe Creative Cloud」を無料で利用できます。
ゆうと:努力や過程を評価してもらえることです。結果だけではなく、たとえ失敗しても過程を大切にして次にどう活かすかを担任やTAとの面談を通してプロジェクトシートで計画を立てることで最終的な成功へのビジョンを描くことができました。
最後に後輩たちへひとことお願いします!
ひな:通学コースのいいところは、学年問わず人と人との距離が非常に近いところです。3年生を間近で見てコミュニケーションを取っておくと、いざ自分が受験生になったときにがっつり構えて臨むことができるので、時間にも心にも余裕ができて有利です。人との出会いが人生を変えることもあるので、たくさんの人とたくさんコミュニケーションを取ってくださいね。
そら:自分の素直な気持ちを大切にしてください。
さわ:N高生だからできること、N高にいる間だからこそ経験できることはたくさんあります。自分の興味や好きなことに正直に、いろいろなことに挑戦してみてください!
ゆうと:N高生活では、自信を持ってさまざまなことに挑戦するべきです。たとえ未知の世界でも自信を持って切り拓くことが、未来のN高生やさまざまな人を助けることにつながるはずです……とは言っても、私はあまり切り拓けなかったので、がんばってください(笑)
さまざまな卒業生が、さまざまな環境で、さまざまな思いを胸に歩んでいきます。
在学中のみなさんも角川ドワンゴ学園での生活を楽しみながら、ゆっくり将来のことを考えてくださいね!